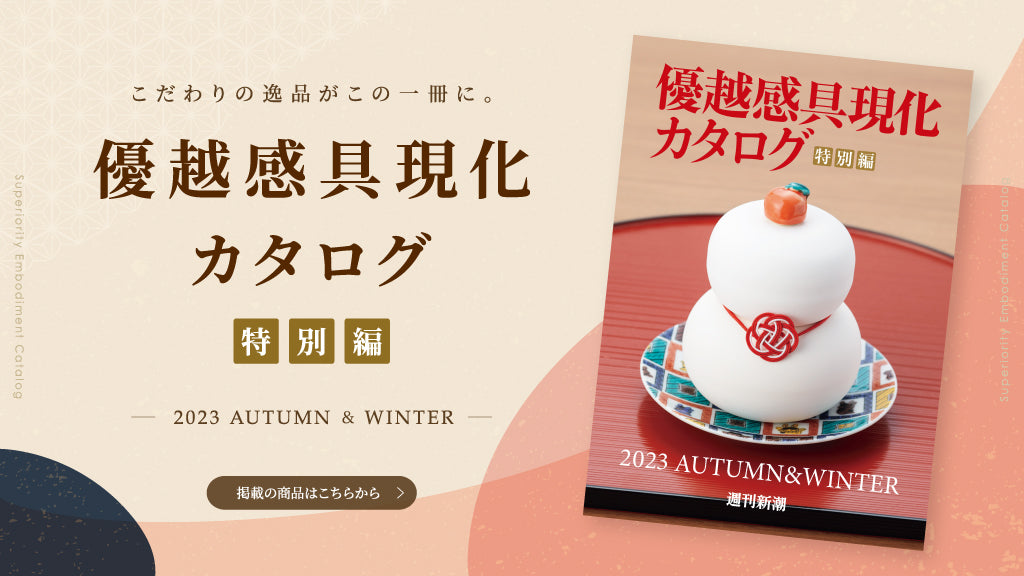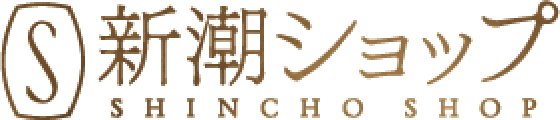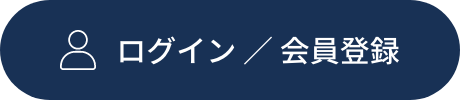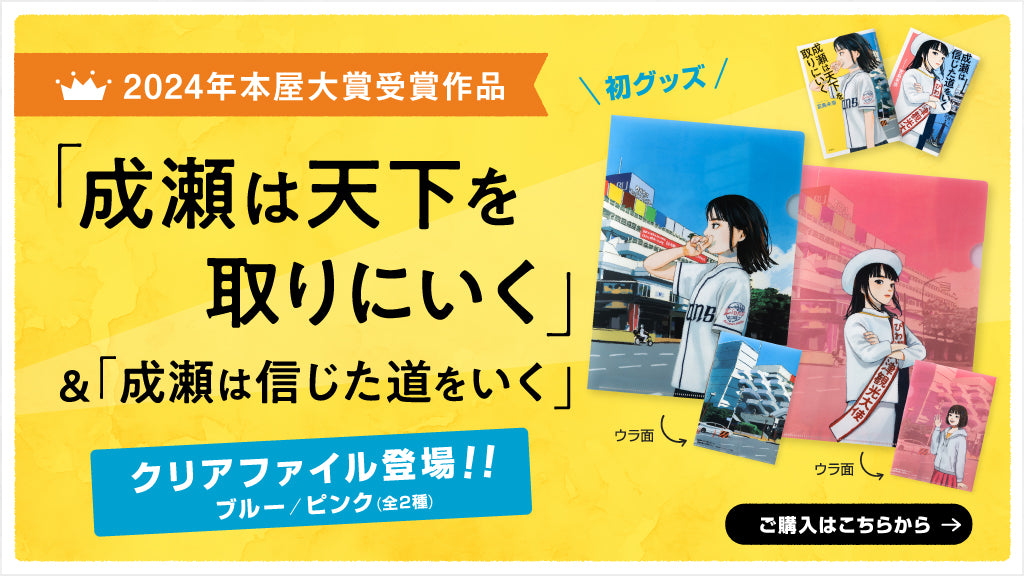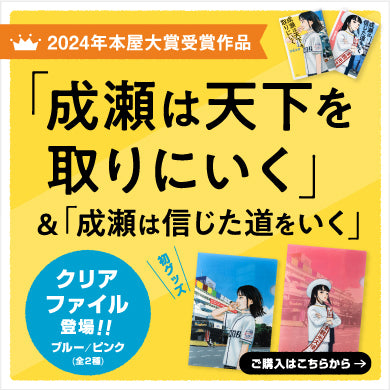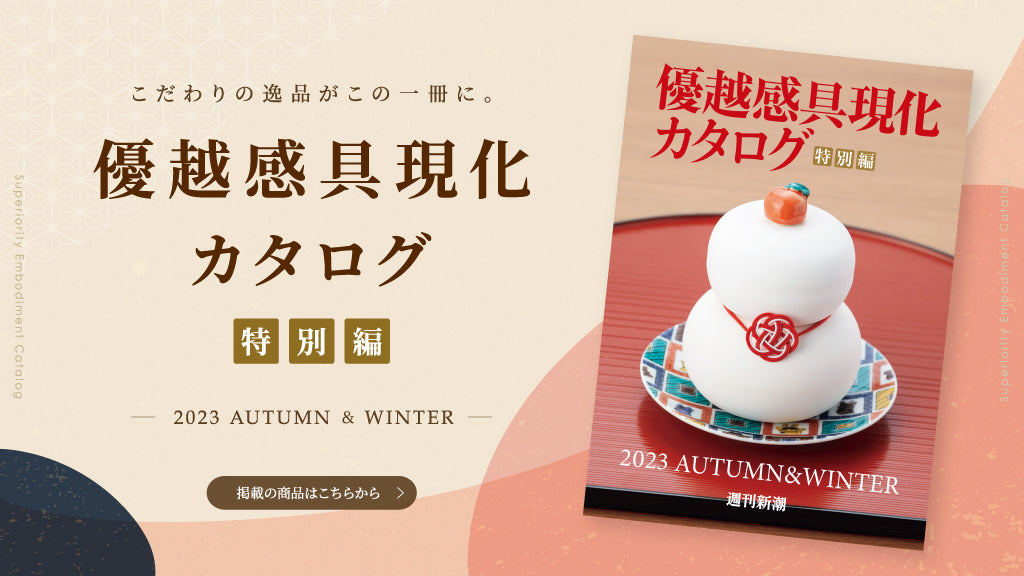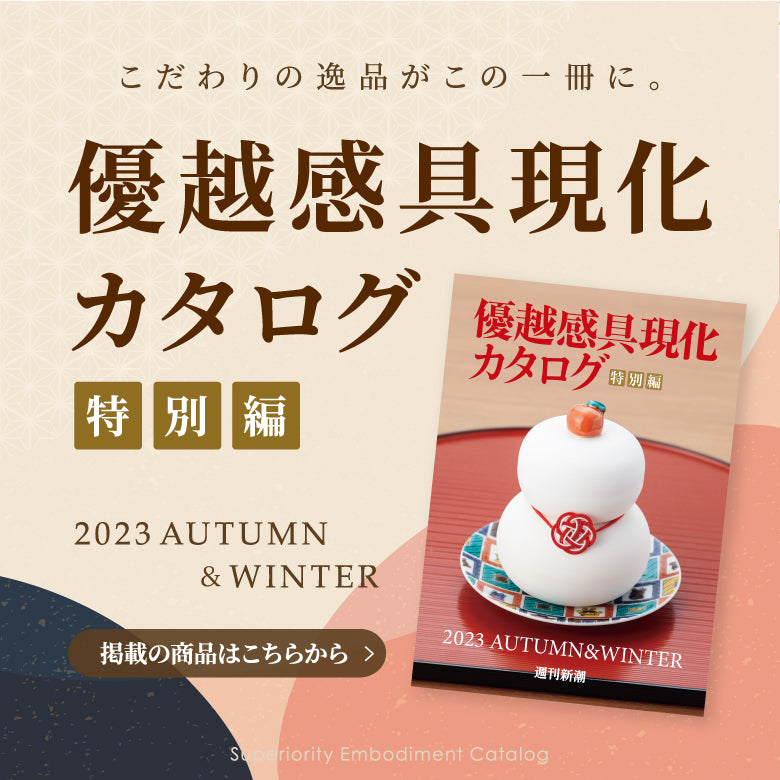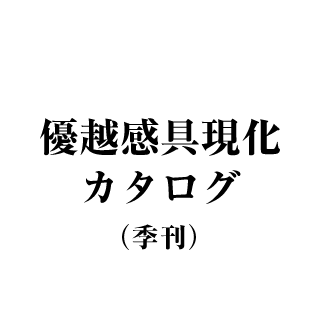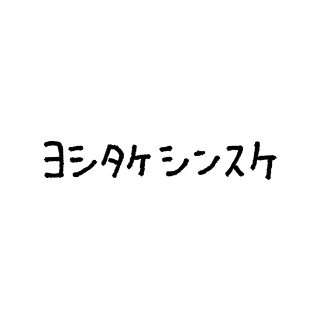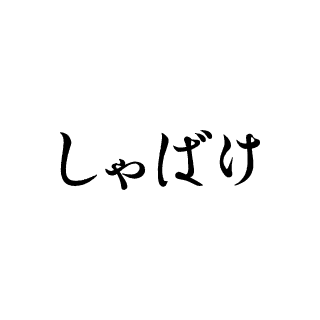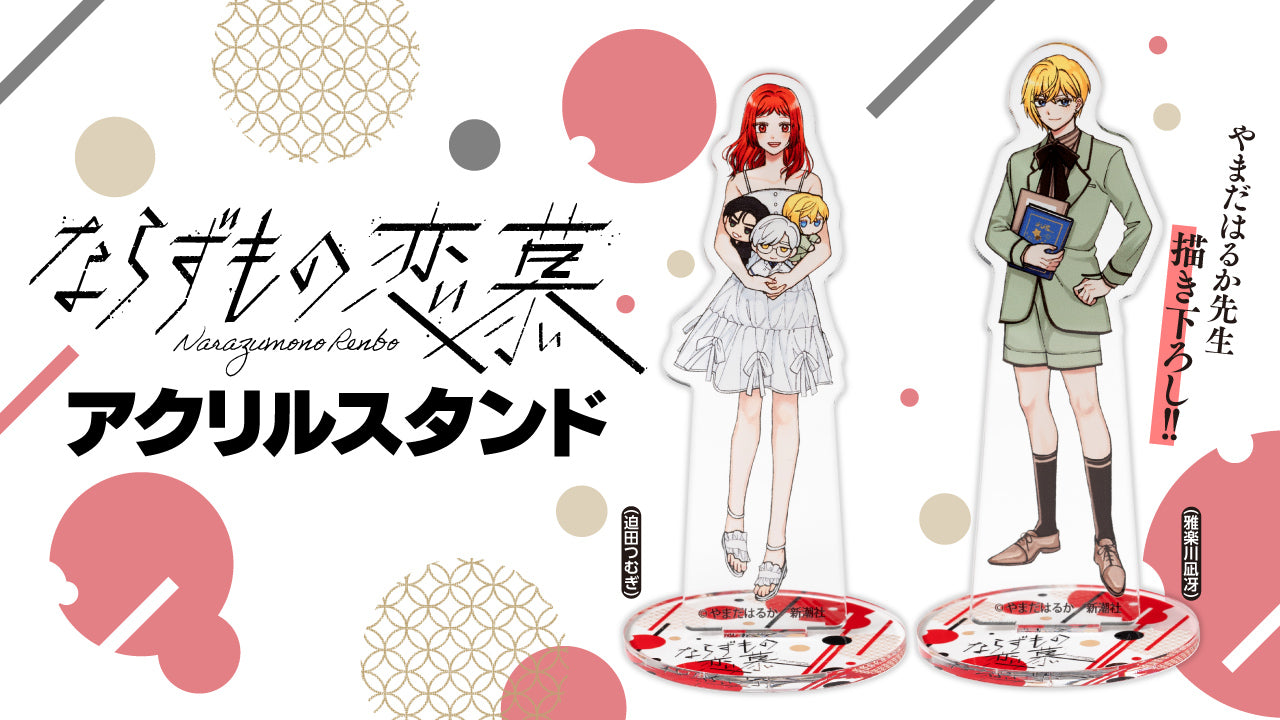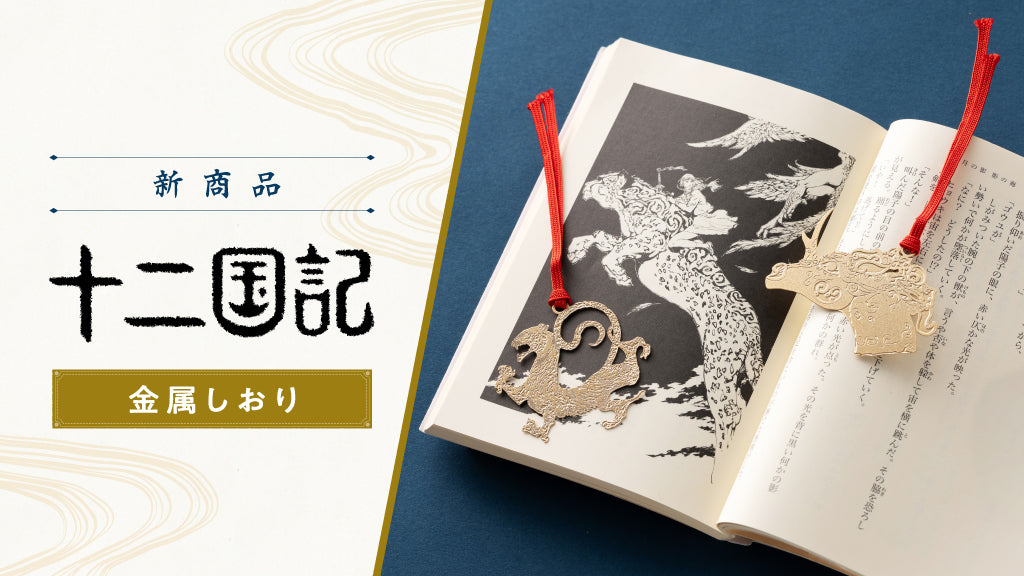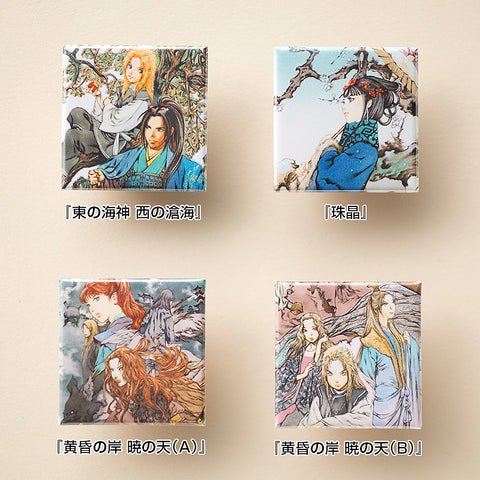新着商品
-
1,100円(税込)
-
1,100円(税込)
-
44,000円(税込)
-
3,500〜円(税込)
円(税込)
3,500〜円(税込) -
792円(税込)
-
792円(税込)
-
792円(税込)
-
2,000円(税込)
-
2,000円(税込)
-
2,000円(税込)
-
10,450円(税込)
-
5,346円(税込)
人気ランキング
385円(税込)
3,500〜円(税込)
円(税込)
3,500〜円(税込)
10,450円(税込)
Mother's Day SALE
-
8,800円(税込)
7,920円(税込)
-
4,950円(税込)
4,455円(税込)
-
5,478円(税込)
4,930円(税込)
-
8,800円(税込)
7,920円(税込)
-
17,600円(税込)
15,840円(税込)
-
5,280円(税込)
4,752円(税込)
-
8,800円(税込)
7,920円(税込)
-
3,300円(税込)
2,970円(税込)
優越感具現化カタログ2023秋冬号
-
3,278円(税込)
-
5,270円(税込)
-
5,054円(税込)
-
3,456円(税込)
-
4,980円(税込)
-
3,780円(税込)
-
3,278円(税込)
-
4,320円(税込)
WEBカタログからご注文
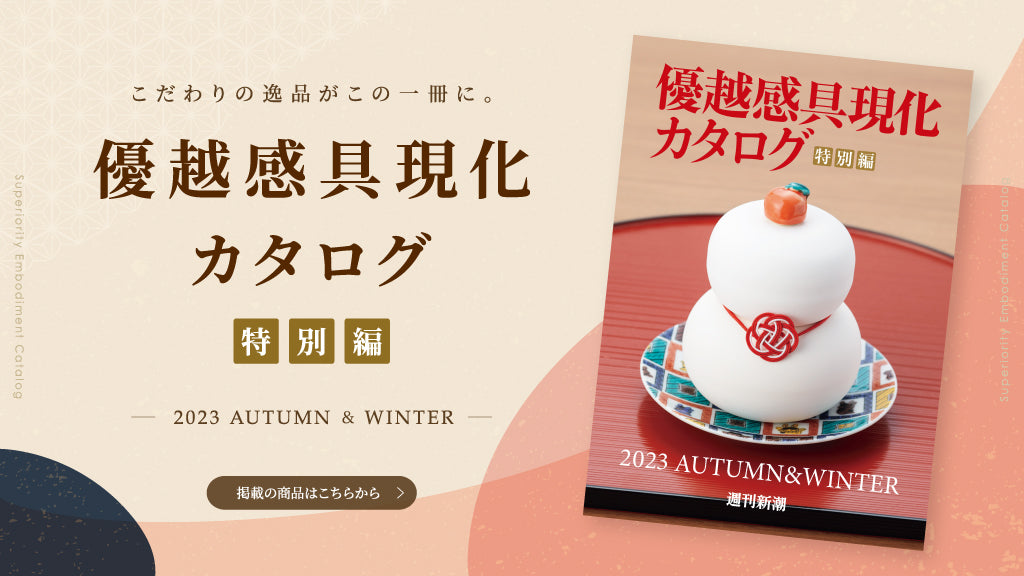
優越感具現化カタログをWEBカタログとして見ることができます。また、カタログ内の商品をクリックすると商品ページが開くので、そのまま注文することもできます。ぜひご活用くださいませ。